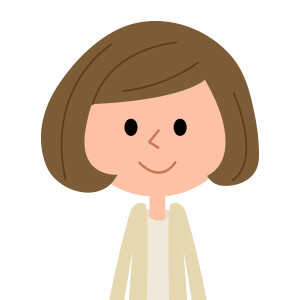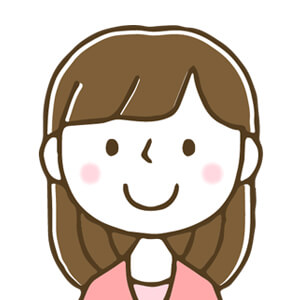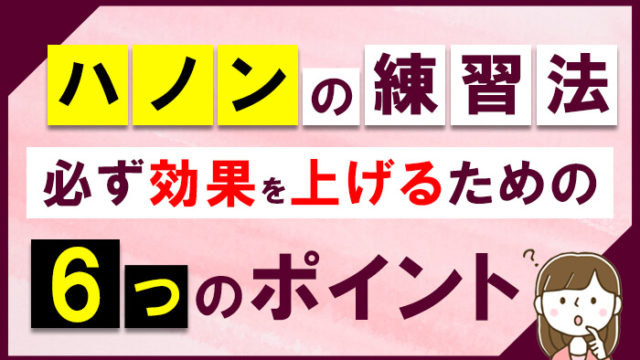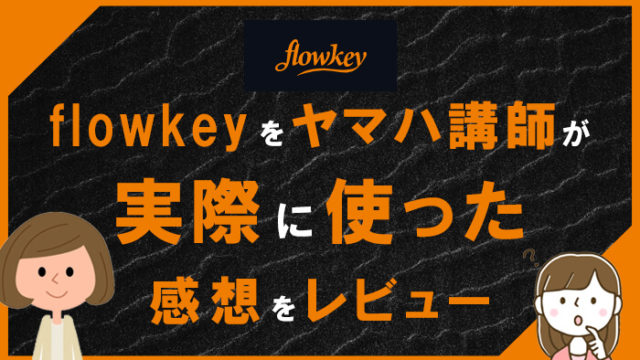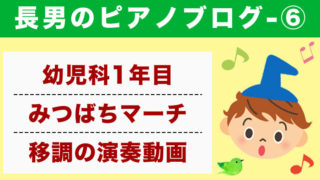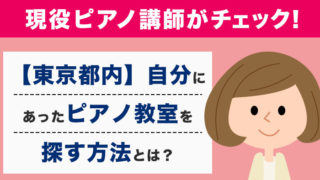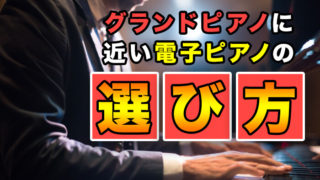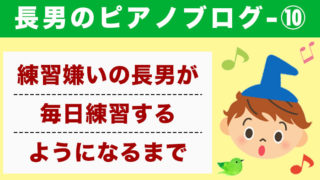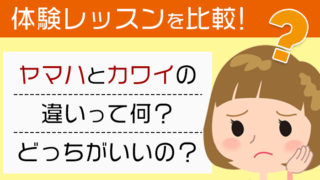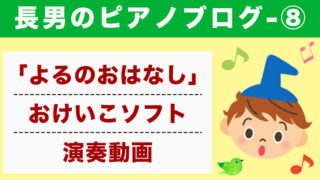私はヤマハ音楽教室でピアノ講師をしています。
そんな経験がある方も少なくないと思います。
今回は、
- 暗譜が飛ぶ理由
- 暗譜を確実にする5つのコツ
について、お伝えしていきます。
なぜ暗譜は飛ぶのか?
なぜ暗譜は飛ぶと思いますか?
それは、身体で覚えているからです。
たくさんたくさん練習していると、いつのまにか「楽譜を見なくても弾けるようになっている」ことがありますよね。
コマなし自転車の練習をするとき、はじめは
と、いろいろなことを考えながら練習しますよね。
でもたくさん練習することで、身体が覚えるので、何も考えなくても乗れるようになるんです。
というのは、自転車と同じで「身体が覚えている」状態。
「ドレミ」や「指の動き」を意識しなくても、身体が動いてくれます。
この状態は、暗譜をする過程として「とても大事」で間違っていません。
ただ、ここで終わってしまうと、緊張したときなどに、暗譜が飛んでしまうことがあるんです。
つまり、
- 身体が覚えている
- 指が覚えている
状態は、暗譜のスタート地点!
暗譜を確実にするためには、身体だけじゃなく、脳にしっかりインプットすることが大事なんです。
それでは、次のパートで暗譜を確実にするためのコツを見ていきましょう。
暗譜を確実にする5つのコツ
暗譜を確実にするコツは次の5つ。
- 両手で弾く
- ゆっくり両手で弾く
- 片手ずつ弾く
- 両手で弾くが、片方の手は音を出さない(鍵盤に触れるだけ)
- 頭の中で両手で弾く
- ①→⑤まで順番にやっていくと効果的
- すべて、楽譜を見ないでやる
- 途中でわからなくなったら、楽譜を開いて確認する
- 「歌いながら弾く」と、覚えやすい
それでは、1つずつ、くわしいやり方を見ていきましょう。
両手で弾く
まずは、「楽譜を見ないで両手で弾く」練習をしましょう。
それまでにたくさん練習していれば、身体が覚えていて、暗譜で弾ける部分も多いかもしれません。
途中で、わからなくなったら、楽譜を開いて確認します。
わからなくなったところは、
- 片手ずつ弾く
- 歌いながら弾く
- 和音記号、調性などを書き込む
と、より覚えやすいですよ。
ゆっくり両手で弾く
つぎに、「楽譜を見ないでゆっくり両手で弾く」練習をします。
テンポを落とすと、指の動きを意識するようになります。
すると、それまで「無意識で弾いていたところ」が
とわからなくなることがあるんです。
テンポを落としたときに「暗譜が飛ぶところ」は、身体は覚えていても脳が覚えていないところ。
楽譜を確認して、覚えなおしましょう。
片手ずつ弾く
つぎは、「楽譜を見ないで片手ずつ弾く」練習をしましょう。
と思っていても、片手ずつにすると弾けなくなるものです。
特に左手!
発表会などで、暗譜が飛びやすいのも左手ですよね。
楽譜を見ないで、
- 左手だけ
- 右手だけ
どちらでも弾けるようにしましょう。
両手で弾くが、片方の手は音を出さない(鍵盤に触れるだけ)
片手ずつの暗譜ができたら、次は「両手で弾くが、片方の手は音を出さない」という練習をします。
右手は普通に弾いて、左手は音を出さずに鍵盤の上で指だけ動かす。
それができたら手を反対にしましょう。
これまた難しくて、脳トレみたいなんですが、やっておくと、かなりしっかり頭に入りますよ。
頭の中で両手で弾く
つぎは、「頭の中で両手で弾く」練習。
ピアノのないところで、エアーで弾きます。
- 音(聴覚)
- 鍵盤(視覚)
- 鍵盤に触れている感覚(触覚)
- 指の動き
など、細かくイメージしてください。
鍵盤がない状態で、イメージするのは難しいですが、自然にイメージできるようになるまで、何度も繰り返しましょう。
発表会で緊張しないための練習法は、発表会で緊張しないために【緊張の予防法】をピアノ講師が伝授をどうぞ。
暗譜を確実にするコツ【番外編】
上のパートでお伝えした5つのコツの他に、暗譜を確実にするための
- コツ
- 練習法
を見ていきましょう。
あなたに「合いそうだな」と思う方法があればやってみてください。
【番外編】のコツは次の4つ。
- 曲の途中から両手で弾き始める(暗譜で)
- アナリーゼをして楽譜に書きこむ
- 楽譜だけを見る時間を作る
- 楽譜を書く
1つずつ、くわしく見ていきましょう。
曲の途中から両手で弾き始める(暗譜で)
一度止まってしまうと、そこから弾き始めるのって難しいですよね。
発表会で、間違えたときに
という経験がある方もいると思います。
どこからでも弾けるようにしておけば安心ですよね。
方法としては
- 誰かに楽譜を指さしてもらい、そこから弾き始める
- 楽譜を見て、目についたところから弾き始める
- あえて途中で止まり、一呼吸あけてから続きを弾く
などがありますよ。
アナリーゼをして楽譜に書きこむ
次のようなことを調べていきます。
- 拍子
- リズム
- 調性
- 形式
- 和声(和音の進行、つなげ方)
とはいえ、細かくアナリーゼをするには時間も知識も必要です。
まずは、
と感じる部分だけでも
- 調
- 和音進行
などを調べてみたり、先生に聞いてみたりしましょう。
- 転調している
- メロディはさっきと同じだけど和音が違う
など、発見があると思います。
そうやって、
- なぜそれまでと違う感じがするのか
- なぜ悲しい感じがするのか
などを、分析をすることでしっかりと頭に入り、暗譜しやすくなりますよ。
それから「形式」も頭に入れておくと暗譜しやすくなります。
例えば、「エリーゼのために」で見ていきましょう。
「エリーゼのために」は、「ミレミレミシレドラ〜」の部分が何度も出てきますよね。
その部分を「A」とすると、次のような形式になっています。
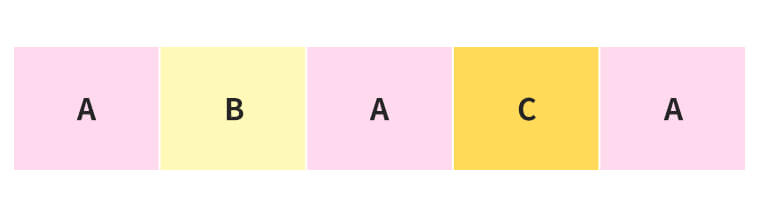
こうやって見ると「エリーゼのために」は、
【「A」「 B」「C」の3つの部分】と【それぞれのつなぎの部分】
を覚えればいいわけです。
曲の「最初から最後まで」いっきに覚えるより、「A」「 B」「C」という「まとまり」で覚えた方が効率がいいですよね。
楽譜を見るだけの時間を作る
「弾くだけ」が、ピアノの練習ではありません。
楽譜を見るだけの時間も作りましょう。
上のパートでお伝えした、「アナリーゼ」をして書き込んだ楽譜だと、より効果的!
- 通勤電車の中
- 弾く練習をする前
などに、楽譜を見る時間を作りましょう。
楽譜を書く
という方には、「楽譜を書く」という方法もあります。
楽譜を見ながら書き写すのではなく、自分で思い出しながら書きましょう。(わからなくなったら楽譜を見てOK!)
曲によっては、ものすごく時間がかかるけど、効果は大きいです。
1曲まるまる書くのではなく、「どうしても覚えられない!」という部分だけでも大丈夫ですよ。
まとめ
暗譜が飛んでしまうのは、身体で覚えているからです。
暗譜を確実にするためには、次の5つの練習をして、しっかりと脳にインプットしましょう。
- 両手で弾く
- ゆっくり両手で弾く
- 片手ずつ弾く
- 両手で弾くが、片方の手は音を出さない(鍵盤に触れるだけ)
- 頭の中で両手で弾く
また、次の4つもやっておくとさらに安心です。
- 曲の途中から両手で弾き始める(暗譜で)
- アナリーゼをして楽譜に書きこむ
- 楽譜だけを見る時間を作る
- 楽譜を書く
暗譜が確実にできたら、発表会で緊張しないための練習もしておきましょう。
発表会で緊張しないために【緊張の予防法】をピアノ講師が伝授を見てくださいね。