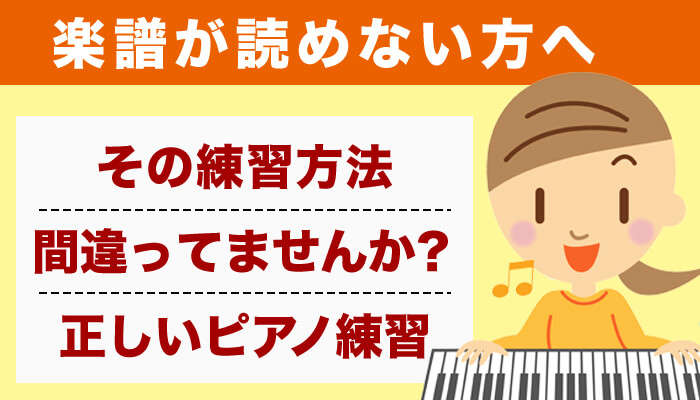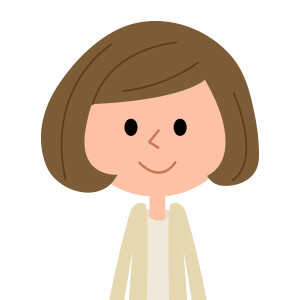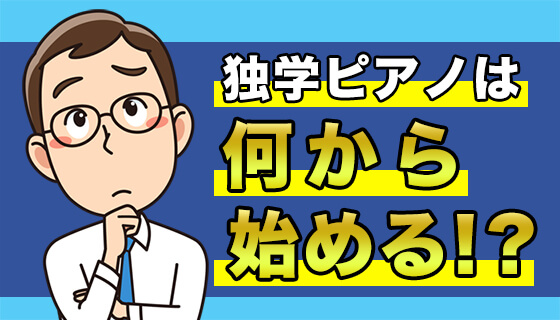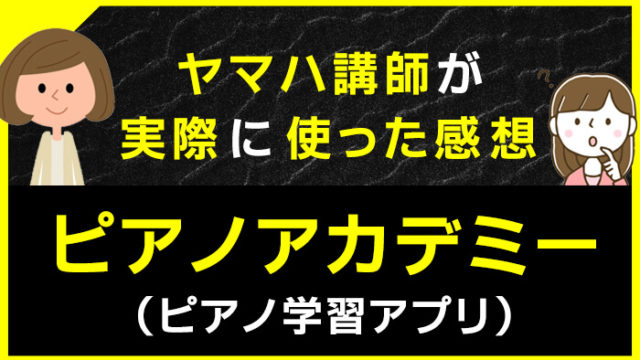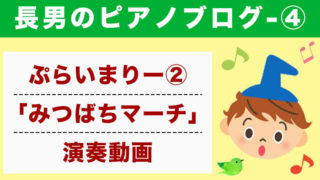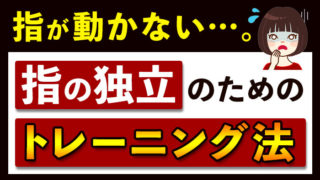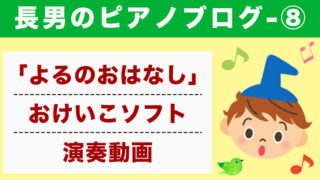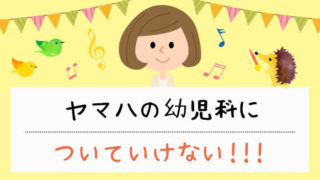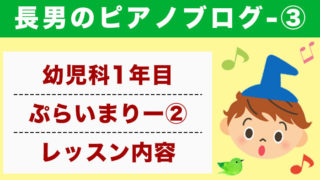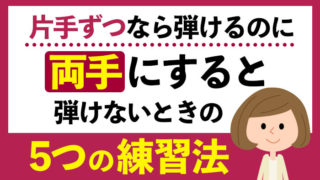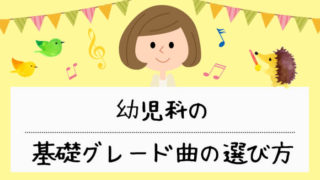私はヤマハ音楽教室で講師をしています。
そんなお悩みをよく聞きます。
楽譜を読んで弾けないのには、原因があります。
そして、原因に合わせて練習をすれば、必ず楽譜が読めるようになりますよ!
それでは、
- 楽譜が読めない原因と練習法
- 楽譜が読めるようになる!おすすめの教本
の順番で解説していきます。
楽譜が読めない原因
楽譜を読んで弾くことができない原因は次の5つ!
- 音符の「高さ」や「長さ」がすぐにわからない
- 鍵盤ではなく楽譜を見て弾くことができない
- 「ト音記号」と「ヘ音記号」を同時に読むことができない
- 楽譜の少し先を見て弾くことができない
- 調号が頭に入っていない
1つずつ、くわしく見ていきましょう。
音符の「高さ」や「長さ」がすぐにわからない
楽譜を読むためには
- 音符の高さ(五線譜での位置)
- 音符(休符)の長さ
- 記号(拍子記号、反復記号etc.)
など「楽譜を読むためのきまり」を覚えなければいけませんよね。
でも、覚えたとしても…
という状態では、楽譜をスラスラ読むことはできません。
「あ・い・う・え・お」の文字を覚えただけでは、文章をスラスラ読むことはできないのと同じです。
それでは、音符をスラスラ読むための練習法を見ていきましょう。
音符をスラスラ読むための練習法
- 音符の高さ
- 音符の長さ
がすぐにわかるようになるために、効果的な練習法は
楽譜を声に出して読む、歌う
です。
それは、小学生のときにやった「音読」と同じ理由だと思います。
音読は、
- 声に出すことで、「目」だけでなく「耳」からも情報が入るため、理解が深まる
- 黙読より脳のたくさんの場所が働き、「前頭前野」も活性化されるため記憶力が高まる
という効果があるそうです。
声に出して楽譜を読む、歌う
その練習を続けることで、読むのがはやくなっていきますよ!
そして、続けるうちに声を出さなくても、頭の中で楽譜が読めるようになっていくんです。
鍵盤ではなく楽譜を見て弾くことができない
という方を見ていると、
楽譜ではなく鍵盤を見ながら弾いている
ということが多いんです。
「弾き間違えないようにしよう!」と思うほど、鍵盤が気になって見てしまう気持ちはわかります。
でも、鍵盤ばかり見ていては、楽譜が読めるようにはなりません。
鍵盤を見ないで弾くための練習法
鍵盤を見ないで弾くために効果的な練習法は…
指のポジションを変えなくても弾ける曲を練習する
です。

たとえば、チューリップの曲。
「ドレミ ドレミ ソミレドレミレ」は、ドレミファソに指を置いたまま弾けますよね。
慣れてきたら、少しずつ離れた鍵盤を弾けるようにしていきましょう。
のちほど、おすすめの教本を紹介しますね。
ト音記号とヘ音記号を同時に読むことができない
という方は
- ト音記号
- ヘ音記号
を同時に読むことができていないかもしれません。
どちらか1段に集中してしまい、2段を同時に見ることができていないということはありませんか?
ト音記号とヘ音記号を同時に読むための練習法
- ト音記号
- ヘ音記号
を同時に読むために効果的な練習法は…
- 右手を歌いながら左手を弾く
- 右手を弾きながら、左手のリズムをたたく
です。
「右手を歌いながら左手を弾く」という練習をすると、両手がとても弾きやすくなりますよ。
また、左手が「和音伴奏」の曲なら、
右手を弾きながら、左手のリズムをたたく
という練習がおすすめです。
楽譜の少し先を見て弾くことができない
楽譜を読んでスラスラ弾くためには、
今、弾いているところ
ではなく、
楽譜の少し先
を見なければいけません。
楽譜の少し先を見て弾くためには、今までお伝えしてきた
- 音符の「高さ」や「長さ」がすぐにわかる
- 鍵盤ではなく楽譜を見ながら弾ける
- ト音記号とヘ音記号を同時に読むことができる
という力が必要です。
その上で、楽譜をスラスラ読むためのトレーニングとして
- かんたんな楽譜をたくさん弾く
- 和音に慣れる
という練習法が効果的です。
「かんたんな楽譜をたくさん弾く」の練習法
今、
- 練習中の曲
- レッスンで習っている曲
より、もっとかんたんな楽譜を用意しましょう。(おすすめの教本はのちほど紹介します。)
練習法ですが、曲を弾く前に
- 拍子
- 調号
- 音部記号
を確認しましょう。
そして…
「同じリズムが続いているな。」
「1段目と3段目は似ているな。」
「ここに臨時記号があるから気をつけよう。」
など、楽譜全体をざっと見てみましょう。
それから、いきなり両手で弾いていきます。
何度か練習して、止まらずに弾けるようになったら、次の曲へ進み、たくさんの曲を弾いていきましょう。
和音に慣れる
上で「かんたんな楽譜をたくさん弾く」という練習法をお伝えしました。
この練習で、和音が伴奏形で出てきたら、分散させずに同時に弾いて確認しましょう。
たとえば…

上のような形で和音が出てきたら
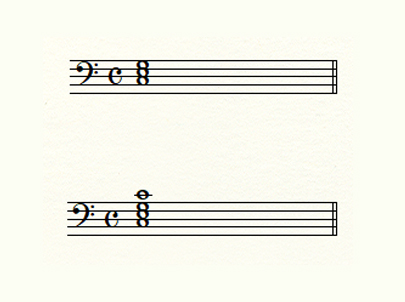
のように、同時に弾きます。
なぜ、このような練習をするかというと…
- 和音を読むのが早くなる
- 和音に合わせて指がパッと動くようになる
から。
「お・に・ぎ・り」と一文字ずつ読んでいた子供が、「おにぎり」と単語で読めるようになり、慣れるにつれて「おにぎりを食べました。」とまとまった文で読めるようになるのと同じ。
かんたんな曲から、たくさん弾いて
- メロディ
- 和音
をまとまりで読めるようにしていきましょう。
調号が頭に入っていない
楽譜は読めるようになってきたけど…
調号が多い曲は、間違えてばかり!
という方も多いと思います。
そんな方は、音階(スケール)をスラスラ弾けるように練習しましょう。
音階(スケール)をスラスラ弾けるようにする
という方が、スケールを練習した方がいい理由は…
「それぞれの調でどの音にシャープやフラットをつけるのか」を覚える(感覚として身につける)ことができるから。
たとえば、シャープが3個ついている曲を弾くとき、
ではなく、
とわかって弾くと、シャープを落としにくくなります。
また、それが感覚として身に付いていれば、シャープを落として弾いてしまった時にも、
と、自分で間違いに気づきやすくなりますよ。
次のパートで、スケールの練習におすすめの教本をお伝えします。
楽譜が読めるようになる!おすすめの教本
楽譜が読めるようになるための効果的な練習法は、次の5つでした。
- 楽譜を声に出して読む、歌う
- 指のポジションを変えなくても弾ける曲を練習する
- 右手を歌いながら左手を弾く
- かんたんな楽譜をたくさん弾く
- スケールの練習をする
この中から、
- 指のポジションを変えなくても弾ける曲を練習する
- かんたんな楽譜をたくさん弾く
- スケールの練習をする
に、おすすめの楽譜や教本をお伝えします。
「指のポジションを変えなくても弾ける曲の練習」におすすめ
「指のポジションを変えなくても弾ける曲」の練習におすすめの教本は、次の2つ。
- 大人のための独習バイエル
- ブラインドタッチで弾けるおとなのための楽しいピアノスタディ
1つずつ、見ていきましょう。
大人のための独習バイエル
「バイエル」は、ピアノ教室でもよく使われる初級のピアノ教本。
それを、独学でピアノを弾く大人のために編集したのが「大人のための独習バイエル」です。
「大人のための独習バイエル」は、
- 上巻
- 下巻
の2冊があります。
上巻の曲は、指のポジションを変えないで弾けるので
鍵盤ではなく楽譜を見ながら弾く
という練習ができますよ。
また、バイエルは、音符の長さをとても理解しやすい教本!
曲を進めていくと下の図のような「音符の長さのきまり」を無理なく覚えていくことができます。
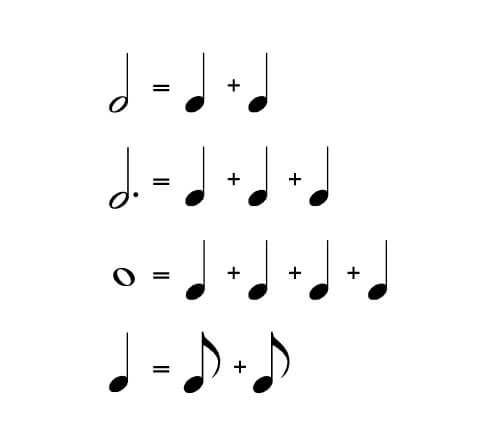
ブラインドタッチで弾けるおとなのための楽しいピアノスタディ
鍵盤ではなく楽譜を見ながら弾く力をつける
そのために作られたのが「ブラインドタッチで弾けるおとなのための楽しいピアノスタディ」です。
3巻まであるんですが、1巻は全てが、指のポジションを変えずに弾ける曲!
2巻からは、少しずつ離れた鍵盤を弾いていきますが、無理なく進められるように、離れすぎない音で作られていますよ。
鍵盤を見なくても弾けるようになる
それを目的に作られた教本なので、
という方におすすめです。
「かんたんな楽譜をたくさん弾く練習」におすすめ
「かんたんな楽譜をたくさん弾く練習」におすすめの楽譜、教本は次の3つ!
- ぷりんと楽譜
- ピアノの上達のための初見練習301
- こどもの初見奏
一つずつ、見ていきましょう。
ぷりんと楽譜
ぷりんと楽譜は、教本ではなく、楽譜を購入できるサイトです。
好きな楽譜を1曲からダウンロード購入することができるんですが、楽譜見放題のサブスク(月額定額制)もあるんです。
- ライトプラン(¥480/月)→5点まで楽譜が見放題
- スタンダードプラン(¥990/月)→無制限、365日いつでも楽譜が見放題
とてもお得なので「かんたんな楽譜をたくさん弾く」という練習法にピッタリですよね。
なぜ、ぷりんと楽譜がおすすめかというと、あなたの好きな曲で練習ができるから。
ピアノ楽譜は10万点以上あり、さまざまなジャンルの楽譜がそろっています。
また、1曲に対して、いくつかの難易度の楽譜が用意されているため、あなたのレベルに合わせて選ぶことができますよ。
>>> ヤマハ「ぷりんと楽譜」を見る
ピアノの上達のための初見練習301
この曲集には
基本練習 → 応用練習 → 総合練習
と難易度順に、初見練習のための曲が301曲入っています。
- 左右3本の指を使う初歩の練習
- ポジションを固定させる基本練習
- 重音や指変えなどの応用練習
- 7つの調を学ぶことができる総合練習
と、1冊で「基本から応用まで」練習できますよ。
こどもの初見奏
1巻〜3巻まであり、
- 1〜2巻→バイエル併用
- 3巻→ツェルニー併用
とレベル別にわかれています。
「スケール練習」におすすめ
「スケール練習」におすすめの教本は、次の2つ。
- ハノンピアノ教本
- バーナムピアノテクニック 全調の練習
1冊ずつ、見ていきましょう。
ハノンピアノ教本
ハノンピアノ教本には、全調(24種)の
- スケール
- アルペジオ
があります。
- 調号
- スケールやアルペジオの指使い
が頭に入っていれば、譜読みだけでなく、曲を弾けるようになるスピードも速くなりますよ!
また、ハノンは「鍵盤を見ないで弾く練習」にもおすすめ。
ということはありませんか?
鍵盤を見ないで弾くためには、
鍵盤と鍵盤の距離の感覚をつかむこと
が大事。
ハノンピアノ教本は、「鍵盤と鍵盤の距離の感覚をつかむ」ために、効果的なんです。
ハノンのスケール、アルペジオは、異名同音の調が入っていないため、全24種です。
異名同音…ド♯とレ♭など、書き方は違うけど、鍵盤上では同じ音のこと。
バーナムピアノテクニック 全調の練習
「バーナムピアノテクニック 全調の練習」は、
という方におすすめ。
全調(30調)の曲が入っていて、曲のはじめにそれぞれの調のスケールが載っています。
ハノンのスケールと違って、1つ1つが短い曲になっていて弾きやすいので、初級の方にもおすすめですよ!